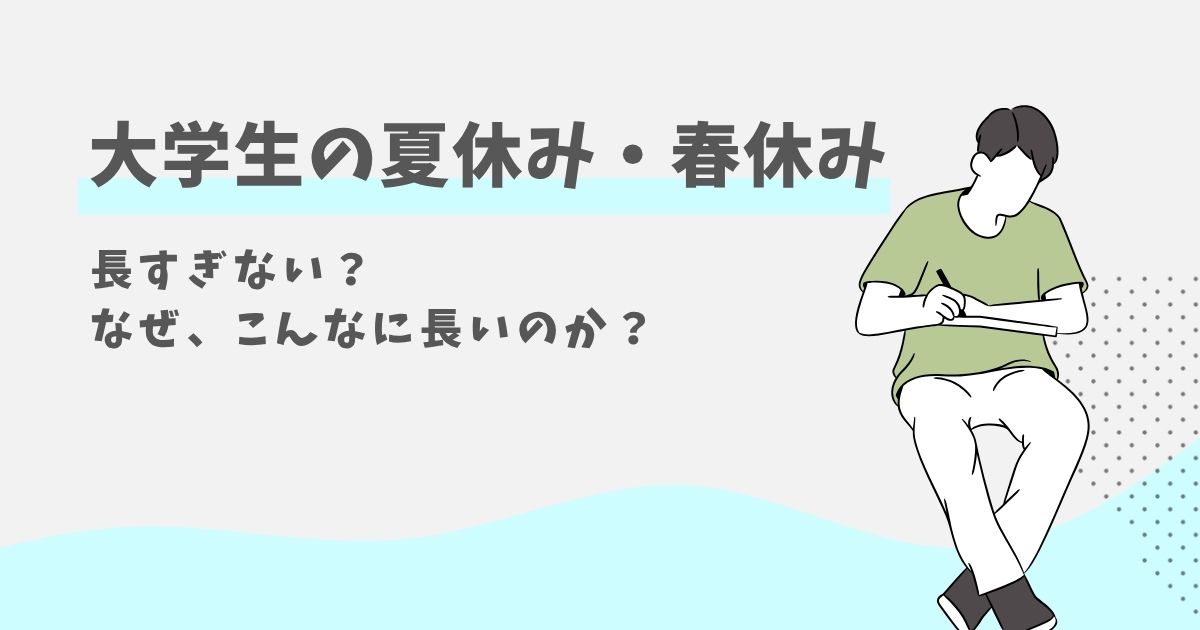高校までの生活に慣れ親しんだ多くの新入生が、大学生活でまず驚くことの一つが「長期休暇の長さ」です。
夏休みや春休みが2か月近くも続くことに、

大学の長期休暇(夏休みと春休み)は、長すぎる・・・。どうしてこんなに長いのか・・・?
と感じる大学生も、少なくありません。
確かに、高校までの長期休暇と比べても、大学の長期休暇は大幅に長く設定されています。
しかし、これは、単なる「学生サービス」や学生を甘やかすための制度ではありません。
大学教育や学問の性質、さらには教員の研究機会の確保など、さまざまな理由によって成り立っているといってよいでしょう。
そこで、この記事では、大学における長期休暇がなぜこれほどまでに長いのか、詳細に見ていきます。
大学生の年間スケジュール

大学の年間スケジュールは、大きく分けて「前期(春学期)」と「後期(秋学期)」に分かれています。
この制度のことを「2学期制」または「セメスター制」と呼ばれることがあります。多くの大学の年間スケジュールは、概ね、以下の通りとなっています。
- 前期(春学期):4月上旬〜7月末
- 夏休み:8月〜9月
- 後期(秋学期):10月上旬〜1月末 ※途中、短い冬休み有
- 春休み:2月〜3月
それぞれの学期の終わりには定期試験期間が設けられ、科目ごとに最終評価が行われます。そして、学期が終わると長期休暇ということになります。
長期休暇(夏休み・春休み)は、約2か月ということになります。「長い」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
多くの大学では、年間授業週数を「各学期15週」と設定しています。つまり、4月〜7月、10月〜1月のそれぞれ約4ヶ月間に15週分の講義を行って、その期間外を「休暇」として確保しているといえます。
学部や大学による違い
同じ大学生といっても、学部や大学によって長期休暇の期間には若干の差があります。
概ね、以下のような傾向があるといえます。
- 文系学部
比較的、定期試験の終了が早く、休暇が長く取られる傾向があります。 - 理系学部
実験や実習が多く、夏休み中も大学に来る必要がある場合もあります。 - 私立大学
大学によっては、祝日も授業を行うなどして試験期間や休暇期間が早めに設定されることがあります。
また、医学部・看護学部など、実習が必要な学部では、病院や学校へ行かなければならず、長期休暇を確保できない場合もあります。
小中高と比較しても休暇が長い?
小中高
小学校・中学校・高校においては、長くても夏休みは40日程度、春休みは2〜3週間というのが一般的です。
しかも、部活動や課題などに追われることになりますので、「自由な時間」はそれほど多くないといえるでしょう。
大学
一方、大学生になると、夏休みは7月〜9月、春休みは2月〜3月というように、それぞれ約2ヶ月(60日間)にわたって休みが取られれます。
これらを合わせると年間約120日、土日祝日を除いても100日以上の「自由時間」が大学生に与えられているという計算になります。
さらに、課題が出されないことがほとんどです。また、仮に課題が出されたとしても、小中高と比べると、少ない場合が多いでしょう。
そのため、大学生の長期休暇は、自由時間であるといってもよいのです。

新入生は、「長期休暇が長い」ことに対して、小中高との違いに驚愕し、カルチャーショックと感じるかもしれません。
しかし、大学の長期休暇中は、単なる遊んでいい時間というわけではありません。
大学(教育)のあり方などが、この長期休暇に深く関係しているのです。その点、以下、詳細に見てまいります。
なぜ、大学の夏休み・春休みは長い

ここからは、なぜ、大学の長期休暇(夏休み・春休み)は長いのかということを見てまいります。理由は、次の3つとなります。
- 大学は研究機関であるため
- 授業以外での自主的な学びも重視されているため
- 自分と向き合える時間の確保のため
それぞれ、詳細に見てまいります。
大学は研究機関であるため
大学教員の仕事は、「授業」だけではありません。研究もせねばならないのです。というのも、大学は、研究機関であるからです。
大学は教育機関であると同時に、研究機関であるということを覚えておきましょう。
大学教員にとって、学部の授業を行いつつ、研究成果を挙げることは、教員としての評価や昇進に直結するため、研究を侮ることはできません。
研究とは何なのか・・・?大学教員において、研究に関する事柄について、以下、挙げます。
- 学術論文の執筆・査読付きジャーナルへの投稿
- 学会での口頭発表・ポスター発表
- 科学研究費(科研費)の申請・獲得
- 国際共同研究の推進
- 学院生の指導・研究室運営
ざっと、以上のようなことを挙げることができます。
しかし、これらは、日常的な授業や会議の合間には進めにくいため、長期休暇中に集中して取り組むということも必要になってきます。

「授業期間中の忙しさをカバーするために、非授業期間を活用して働く」というのが実態に近いといえます、
また、大学の夏休み・春休み期間中には、学会が多数開催される傾向があります。
学会の目的は、研究者が互いに研究成果を発表し、議論することで、学術の発展と知識の共有を促進すること。
つまり、大学が研究機関であることに鑑みると、学会の開催は非常に重要といえます。
しかし、こうした学会を授業期間中に開催するのは、時間があまりなく難しいといえます。
そこで、大学の教員が多くの時間を割ける、夏休み・春休みの期間に開催されることが多いのです。
大学教員は研究者でもあります。大学の夏休み・春休みがなければ、研究に時間を割くのが難しくなります。大学は研究機関であるために、長期休暇が長いともいえるでしょう。
なお、「長期休暇=教員が休んでいる」と考えるのは誤りです。
授業以外での自主的な学びも重視されているため
高校までの教育では「授業中に教えられたことを覚える」ことが中心ですが、大学ではそれとは異なります。
大学教育では、「学びを自ら設計し、自分で考える」ことが求められるます。
もちろん、講義での知識のインプットは必要ではありますが、自分の関心に基づいて探究し、知識を応用する力こそが大学で育てられるべき資質であるのです。
そのため、大学の教育設計では「授業時間外の学習」が前提となっています。文部科学省の「大学設置基準」では、1単位を「授業15時間+自学自習30時間」と定義しており、講義時間の2倍の時間を自学に費やすことが想定されています。
では、その自学自習はいつ行うのか。
日々の授業期間中はレポート、予習復習、サークル活動などに追われ、まとまった自由時間を取りにくいといえます。

本来は、授業時間の2倍の時間の自学自習を授業期間中に行う必要があります。そうすることにより、単位が認定されるというのが原則ですが、実際は、なかなか難しいという声も多いです。
そこで、長期休暇である夏休みや春休みこそが、自学自習の時間として設けられているということもできるでしょう。
また、夏休み・春休み期間中に、
- 海外留学、語学研修
- NPO・NGOの活動
- 地域でのボランティアやまちづくり活動
- 実習、インターン
- 英語や第二外国語の集中講座
- 他大学との合同授業
などに参加するのもよいでしょう。
大学生の学びは、講義や研究にとどまるべきではありません。
時間を確保することが容易な夏休み・春休みは、以上のような自主的な学習や挑戦の舞台にすることができるともいえます。
大学教育の本質は「主体的な学び」にあります。そのため、学生に、自律的活動の時間も確保することも大切なことです。
長期期間中、学生は、授業期間中には行うことができない「主体的な学び」が求められます。
自分と向き合える時間の確保のため
上記と共通する点も多いですが、最後は、「自分と向き合える時間の確保」という観点から述べていきます。
心理学では、大学生の時期を「モラトリアム(猶予期間)」と表現することがあります。社会的な責任を一時的に免除され、自分の将来や生き方を模索する時間という意味です。

長期休暇は、まさにこのモラトリアムを象徴する時間です。
つまり、大学生は、
- 社会人になる前に、何を考えるか
- どんな生き方をしたいのか
- 将来に向けて何を準備すべきか
という「人生の問い」に対して向き合う必要があるのです。
そのためには、「試行錯誤の時間が必要であり、それを担保しているのが夏休み・春休みである」と考えることもできます。
社会人から見ると大学生の長期休暇は「うらやましい」「甘え」に見えることもあるでしょう。
しかし、学生側から見れば、それは単なる遊びではなく、自立へ向けた準備期間なのです。
むしろ、大学生にとっての休暇は、「自分の人生をデザインするための準備期間である」と捉え直す必要があると思われます。
ということで、いかがでしたでしょうか。ここまで、なぜ、大学の長期休暇(夏休み・春休み)が長いのかということを述べてきました。
大学教員、大学生双方にとって、長期休暇は必要であるということになるのです。
しかし、一方で、大学生は休みすぎだと思う方もいらっしゃるでしょう。その点について、これから、述べていきましょう。
大学生は休みすぎ?

社会ではしばしば「大学生の休暇が長すぎる」「大学生は休みすぎ」といった声が上がります。
ここまで読んできた方ならば、お察しかもしれませんが、これは高校や社会人の時間感覚からの一面的な批判です。大学生の本質的な学び方を見落としているということができます。
大学教育は「自分で学び、自分で決める力」を育てる場であるので、そのプロセスに時間的な猶予が不可欠なのです。そうした意味で、長い夏休み・春休みがあるということになります。
一方で、長期休暇は「遊ぶだけ」と考えている大学生がいるのも事実でしょう。
しかし、これまで述べてきました通り、大学の長期休暇(夏休み・春休み)は、遊ぶためにあるわけではありません。
あくまで、大学生の本分は「勉強」であるということは、絶対に忘れてはなりません。
関連記事:「【青春できる?】大学生は青春を謳歌すべきなのか?」(内部リンク)
まとめ
大学生の夏休み・春休みが約2か月と長いのは、学生に「遊び時間」を提供するため、というわけでは全くありません。
以下の理由から、長期休暇が必要なのです。
- 大学は研究機関であることから教員が研究するために必要
- 大学教育の本質が「主体的な学び」にあるため、自律的活動の時間が必要
- モラトリアム人間である自分と向き合う時間が必要
長期休暇は、「自由をどう使うか」という教育そのものなのです。休みの時間こそが、大学生が「何者かになる」準備期間なのです。
ただし、繰り返しになりますが、長期休暇は、学生が遊ぶ時間ではないので、その点は十分に留意しましょう。