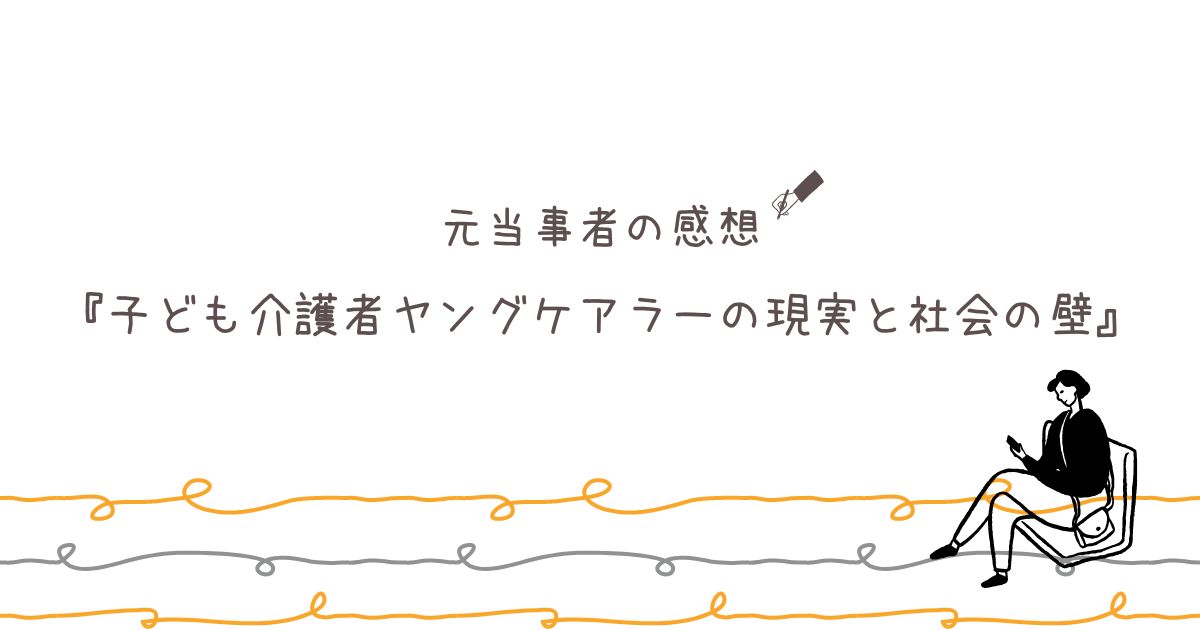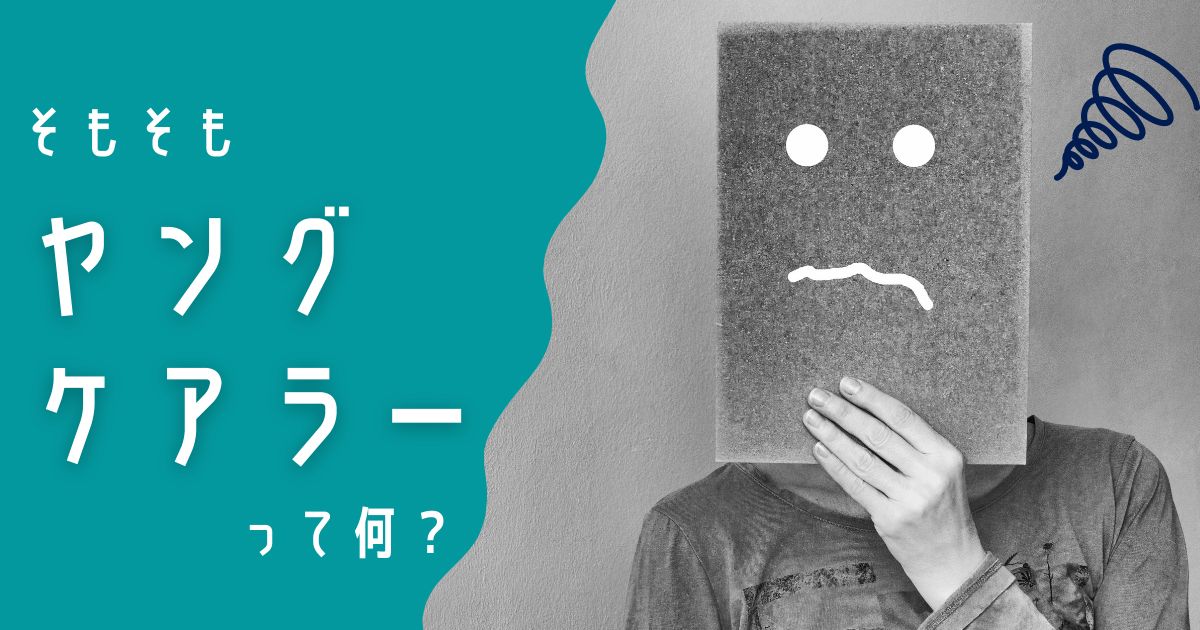元ヤングケアラー・若者ケアラー執筆記事です。
当サイトでは、私の介護(広い意味でケア)経験などを発信していますが、介護経験というのは、本当に多種多様なのです。それ故、情報発信をすると、どうしても、主観的な内容になりがちです。
したがって、私は、できる限り、客観的な情報を入手するために、ヤングケアラー関連の本を、いろいろと読んでおります。
そこで、これからは、元当事者目線で、ヤングケアラー関連本についての感想を記してまいります。
第1弾は、濱島淑惠著『子ども介護者 ヤングケアラーの現実と社会の壁』を紹介いたします。新書ということだけあって、比較的、読みやすい本となっております。
ヤングケアラーの現状や課題がわかりやすくまとめられていますので、ぜひ、手に取っていただければと思います。
タイトルの「子ども介護者」について

本書のタイトルは『子ども介護者 ヤングケアラーの現実と社会の壁』です。「ヤングケアラー」という言葉が副題に入っていますが、気になったのが「介護者」という言葉です。
というのも「介護」は「ケア」よりも狭い意味をさすため、果たしてどうなのだろうかと感じたのです。
しかし、第1章の第1節で、早速、タイトルの「介護」という言葉について解説がなされていました。
本来、介護とはこうした「全人的なケア」を意味するものである。
濱島(2021)p. 22
「介護をする」といっても、いわゆる、身体的介護だけでなく、家の家事を行ったり、見守りを行ったりするなどなど、様々なことを行う必要があるのです。
身体的なケアだけでなく、それに付随する様々なことを含めて、本来は「介護」と呼ばれるべきということです。
このようにとらえると、タイトルの「介護」という言葉にも、納得です。
ヤングケアラーは、身体的ケアをする人だけではない
「子ども介護者」という言葉について、少し気になったと述べましたが、ヤングケアラーについても、同様に、身体的なケアをする人だけを指すわけではありません。
身体的なケア以外に、例えば、上述の通り、家事や見守り、話し相手になることや心のケア、兄弟の世話、通訳などなどをしている子どもについても、ヤングケアラーとなります。
ヤングケアラーと一言で言っても、彼らがやっていることは本当に多様なのです。
この本における、ヤングケアラーは、以下の通りです。
本書におけるヤングケアラーとは、「何らかの疾患、障がいを有する、高齢である、または幼い家族・親族がいて、そのためにケア(家族、介護、感情的サポート、通訳等)を担っている子ども・若者」というイメージでとらえて、読んでもらえたらと思う。
濱島(2021)p. 34
例えば、私の場合は、高校1年生のときに、母が骨肉腫(骨のがん)になり、脚が不自由に。そのまま、母ががんで他界する大学4年生になるまで、母のケアや家の家事などをやってきました。
年の離れた弟もいたので、もちろん、弟の面倒も見てもいました。
18歳未満のケアラーをヤングケアラーとして、18歳以上から概ね30歳のケアラーのことを「若者ケアラー」という場合があります。
幸いにして、私の場合、親族や地域の人とのつながりがあったので、介護保険(第2号被保険者)を活用したり、ケアを手伝ってもらったりするなどして、何とか乗り切ることができました。
しかし、中には、孤立してしまったり、支援を受けられなかったりする人もいるわけです。
また、この本でも述べられていますが、ヤングケアラーは、手伝いではなく、ケアをやらざるを得ない状況の人であるため、自身の学業や健康よりもケアを優先せねばなりません。
それに伴う、悪影響も懸念されるわけです。
第2章では著者が実施をした調査、また、第3章では研究をするうえで会ってきたヤングケアラーの実例について述べられていますが、当事者の想いも含めて、いかに、ヤングケアラーが多様なのだろうかということがわかるかと思います。
ヤングケアラーの特徴として特筆すべきこと
第2章の調査、第3章の実例で、ヤングケアラーは多様だというこを確認することができるのですが、一方で、特徴(共通する点)もあります。
ヤングケアラーの特徴について述べられているのが第4章です。
特徴の中で、当事者以外の人が読んだら「本当かよ?」と思われる内容のものを、私の経験をもとに、少し深堀りしていきます。
本人も周囲もケアだとは気づきにくい
第4章の最初に述べられているのが「本人も周囲もケアだとは気づきにくい」ということです。
ここでは、特に「本人」に焦点を当てます。
確かに、身体的なケアを長時間にわたって行っているヤングケアラーならば、自分はケアをしていると自認できると思われるかもしれません。
しかし、冒頭に述べた通り、ケアは本当に多様です。例えば、家の家事を全面的に担うこと。これを、子どもたちは、「ケア(広い意味での介護)」と捉えることはできるでしょうか。
なかなか、難しいと思います。
身体的な介護をやっている人からしても、そもそも、愛する家族をケアすることは当たり前のことだと思い、ヤングケアラーだとは気づかないこともあるでしょう。
気づく気づかない以前に、自分をヤングケアラーとしてみなしてほしくない、分類されてほしくないという人もいます。ヤングケアラーの想いも多様です。
ちなみに、私の場合は、高校生の時点で、ヤングケアラーだと気付いていました。
というより、新聞を読む習慣があり、ヤングケアラーに関する記事を目にしてしまったのです。このころは、まだ、ヤングケアラーの存在がほとんど知られていなかったときのことです。
当該新聞は、早い段階で、ヤングケアラーについて取り上げていました。

「こんな些細なことでも、ヤングケアラーになるのか…」というのが、初めて、ヤングケアラーについて知ったときの感想でした。
誰にも話していない

第4章では自身がヤングケアラーであることを「誰にも話していない」ということもでてきます。自身がヤングケアラーであることは、口外をすることは、ほとんどないのです。
実は、私も、そうでした。
自身がケアをしていることを周囲に伝えると、場合によっては、支援につながったり、励ましてくれたりするのではないかと考えるのではないでしょうか。
しかしながら、ヤングケアラーへの理解がなければ、期待をすることはできません。
ヤングケアラーについては、一定数存在するという調査はあるものの、とはいえ、少数派です。ケアや介護について、しっかりと理解をしてくれる人はなかなかいないのです。

仮に、ケアについて話しても、冷淡に対応されるということもあるかもしれません・・・。
終章の2節で記載がありますが、周囲の理解というのが大切になってきます。
周囲の理解があれば、ヤングケアラーが自身の状況について話しやすくなるでしょうし、より迅速に支援につなげることができるかもしれません。
終章では、ヤングケアラーの支援策について触れられていますが、私自身は、まず、周囲がヤングケアラーについての理解を深めることが最も大切だと思っています。
ヤングケアラーは可哀想なのか
最後に、著者が、あとがきで述べていたことについて触れて、締めといたします。
ズバリ、ヤングケアラーは可哀想なのかという問題です。
ヤングケアラーについて、ネガティブな面が強調され、国や地方自治体も支援に乗り出しています。
しかし、ヤングケアラー自身は、ケアをすることを嫌だと思っているのでしょうか。自分は、他とは違う、可哀想な存在だと思っているのでしょうか。
必ずしもそうではないでしょう。私も、当時、ケアをすることは嫌だとは全く思っていませんでした。
かといって、ポジティブに捉えるのも違います。
社会が変わることで、彼らはポジティブでもネガティブでもない、ただのケアを担う子ども、若者でいられるのかもしれない。
濱島(2021)p.231
普通の存在として扱われたいというヤングケアラーの気持ち、元当事者の私自身もすごく共感できます。
結局は、皆が、ヤングケアラーやケア・介護への理解を深めることが最も大切になってくると思います。
本でも触れられていましたが、今後、少子高齢化がますます進んでいきます。ヤングケアラーも増えていくかもしれません。
ヤングケアラーが生きづらい社会にならないように、元当事者として何ができるか、考えていきたいと思います。