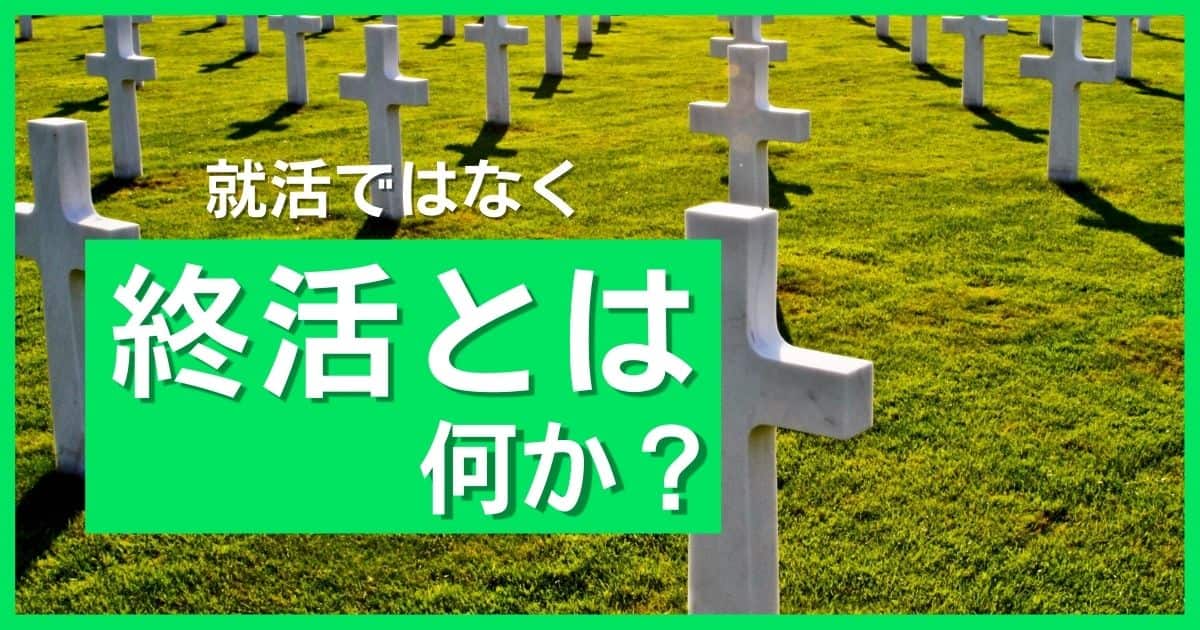「終活」ではなく、「就活」をする年代である、当サイト管理人のはしです。
そんな私も、母親の死をきっかけに、「就活」ではなく「終活」に興味を持つようになりました。

終活は、早くやっておいて、損はありません。
そんな、終活という言葉は、いつから使われているのでしょうか。
実は、結構、新しい言葉なのです。
そして、終活とは何なのかということも、簡単に解説をいたします。
終活は、死を連想させるので、ネガティブなイメージをお持ちだとおもいます。
しかし、終活を行うことは、大きな意味があることです。
この記事を見てわかること
- 終活とは何なのか
- 終活という言葉の起源とは
- なぜ、終活?
終活について、概観してまいります。
終活とは
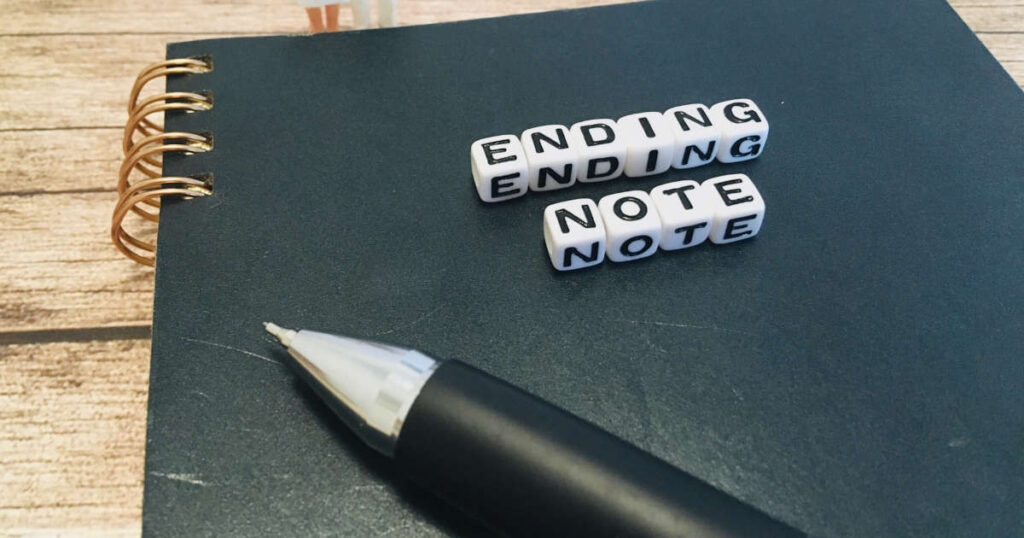
終活とは、人生の終わりのための活動のことです。
人生の終わりといったことを聞くと、死が連想され、ネガティブなイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。
確かに、死と向き合うことになるため、ネガティブな気持ちになるかもしれません。

終活をしても、所詮、自分の死後に関わること。「まだ早い」などとして、終活を後回しにしていないでしょうか。
しかし、終活は、むしろ、自分を見つめて、今後の自身の人生をよりよくするものです。
終活を行うことによって、死をポジティブに考えることができるようになります。
終活について思い立った時に、終活を始めてみるのがよいでしょう。例えば、近親者が他界したり、大きな病気にかかったりすると、アクションのタイミングと言えるでしょう。
終活は、具体的に何をすること?

終活について、具体的に述べていきましょう。
終活とは、具体的にどのようなことを指すのでしょうか。
ここでは、以下の通り、代表的なやり方として4つ紹介します。
お墓・葬儀の準備をする
当初、終活というと、まず、自分のお墓や葬儀の準備をすることを指していました。
もちろん、現在においても、自分のお墓や葬儀の準備をしておくことは大切なことです。
お墓の場合は、先祖代々の家族墓に入るのか、それとも、納骨堂に入るのか、はたまた、散骨をしてもらうのか、自分が希望するものを選んでおきましょう。

お墓は家族とも関わってくるので、家族といっしょに考えるのがよいでしょう。
葬儀についても準備をしておくべきです。
葬儀の形式をどうするか、それぞれ希望があることでしょう。自分らしい葬儀にするためにも、そうしたことを検討しておきましょう。
さらに、葬儀は、費用がかかります。銀行預金口座が凍結される前に、現金化をしておくといったこをやっておくべきです。
加えて、亡くなってから葬儀までは時間がありません。遺族・親族からすると、事前準備をしていると、それだけ、余裕ができます。あらかじめ、見積もりをしておくのもよいかもしれません。

私の経験談ですが、葬儀については全く知識がなかったため、母の死後、とりあえず、電話帳に書かれている業者に葬儀をやってもらいました。本当にこれでよかったのかはわかりません。
生前整理を行う
生きているうちに、自分の持ち物や財産などを整理して、不要なものは処分しておきましょう。
こうした、生前整理は、死後、家族の負担を減らす目的があります。
しかし、同時に、自分の思い出に向き合うということになるため、今後の人生をより良くする効果もあります。

財産の整理をするときは、遺言書の作成といったことも行う必要があります。
エンディングノートを作成する
終活といえば、エンディングノートという印象をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
2011年に、「エンディングノート」という映画が公開され、より多くの人に知られるようになりました。
エンディングノートには、人生の終わりをどう迎えたいのかということを書いておきましょう。
上で述べた葬儀やお墓のことや財産について記すことをおすすめします。
エンディングノートは、遺言書とは異なり、法的拘束力はありません。
ただ、誤解してはならないことがあります。
エンディングノートは、死後のことについて親族などに伝えることだけが目的ではありません。
今後、より良い日々を過ごすために、自分がどう生きるかということを探ることも目的の1つです。
エンディングノートを書いて、自分の人生について見つめ直すきっかけとなるのです。

エンディングノートには、書く項目が多数あります。自分のペースで、最も惹かれた項目から書いていきましょう。
終活については、その他にも、やっておいた方がよいことは多数あります。
早い時期からやっておいて損はありません。
終活を行って、今後の自分の人生をより良いものにしていきましょう。
死についてポジティブに考えられたらより良いでしょう。
「終活」という言葉の起源

「就活」ではなく、「終活」という言葉は、いつ頃から使われてきたのでしょうか。
「終活」という言葉の起源はどこにあるのでしょうか。
「終活」という言葉は週刊誌が起源
実は、「終活」という言葉が最初に登場したのは、2009年、週刊誌でした。
その週刊誌とは、『週刊朝日』2009年8月14日号です。
「短期集中連載 現代終活事情 おわりよければすべてよし 変わりゆく葬儀のかたち」というコラムが掲載されたのです。
7月14日号以降、数回に渡って連載がなされます。葬儀に焦点を当てたコラムとなっています。
したがって、「終活」という言葉の生みの親は、「週刊朝日」元編集長の佐々木広人氏といわれています。
2012年には流行語トップテンになる
そして、終活は、ブームとなってきます。
2012年には、ユーキャンの新語・流行語大賞のトップテンに選ばれています。
2012年の新語・流行語
- iPS細胞
- 維新
- LCC
- 終活
- 第3極
- 近いうちに…
- 手ぶらで帰らすわけにはいかない
- 東京ソラマチ
- 爆弾低気圧
- ワイルドだろぉ【大賞】
「終活」の受賞者は、流通ジャーナリストの故・金子哲雄氏となっています。
というのも、金子氏は、亡くなる前に、自身の葬儀やお墓の準備など、「終活」といえる活動をしていたからです。
金子氏は、終活の一例を示されたのです。
終活が、新語・流行語に選ばれたように、この頃に、終活ブームが到来しました。

そして、最近は、終活が当たり前になりつつあるように見えます。
なぜ、終活?

なぜ、終活がブームになり、今や、終活が普通になりつつあるのでしょうか。
終活の背景については、いくつか指摘できますが、最も大きな社会的背景として、少子高齢化があります。
かつての高齢者は、子どもなどの家族に面倒を見てもらったり介護をしてもらったりして、最期を迎えるということが普通でした。
しかし、最近は、血縁関係が薄れ、家族や周囲に迷惑をかけたくないという高齢者が増えています。
ひとり暮らしの高齢者も少なくありません。
家族や周囲にできるだけ迷惑をかけないようにするため、終活を行うという方が多いのです。

少子化も進んでいて、子どもがいない、もしくは、一人しかいないという高齢者もいます。子どもの負担を減らすために、終活をするという方も少なくありません。
まとめ:終活は自分の人生をより良いものにする
終活についてネガティブなイメージを抱いていて、終活をやりたくないという方もいらっしゃるかと思います。
確かに、家族や周囲の人に迷惑をかけてはならないという意味で、終活をやっておくことは意味はあります。
しかし、それ以上に、終活は、自分の今後の人生をより良いものにするといえるでしょう。
当記事を見ている方、今が、終活を始めるチャンスです。ぜひ、終活を行ってみてください。