
大学には行くべきか、行かなくてもいいのか?
この問いは、高校生にとって避けて通ることのできないテーマの一つです。
親や先生は「大学に行っておいた方がいい」と口をそろえることが多いですが、その理由を具体的に説明できる大人は意外に多くありません。
世間では「なんとなく大学へ進学する」という人が依然として多い一方で、大学に行かなくても成功する人も、一定数、存在しているため、「大学に行く意味なんてあるの?」という疑問を持つ人もいます。
日本では、現在、大学進学率が約60%となっています。つまり、高校のクラスの半分以上が大学に進む時代です。
しかし、金魚の糞のように、「多数派だから大学に行く」という理由では、大学に行く理由として適切ではないでしょう。
では、なぜ人は大学に行くのでしょうか?大学で何が得られ、どんな価値があるのでしょうか?
ここでは、「大学に行く意味」「行く理由」「行くメリット」を、学問的・社会的・経済的・心理的観点から、掘り下げます。
大学進学という選択を、自分の言葉で話すことができるようになっていただけますと幸いです。
「大学に行く意味」を問う

日本では1990年代以降、大学進学率が急上昇しました。
1970年代には30%台だった進学率が、2020年代には約60%となっています。
この背景には、「高学歴=安定」という社会の構造がありました。
高度経済成長期、日本社会では
いい大学→いい会社→安定した生活
という一本道のキャリアモデルが成立していたのです。
しかし、21世紀に入り、この構図は大きく崩れました。
終身雇用の崩壊、転職の一般化、グローバル化の加速、そして、最近叫ばれているのがAIの登場。
「学士」という学歴があっても、必ずしも、希望の職に就けないという人もいて、「大学に行っても意味がない」という声も聞かれるようになっています。
それ故に、今は「大学に行くのが当たり前」ではなく、「大学に行くのも選択肢の一つ」という時代です。

だからこそ、自分はなぜ大学に行くのかを、自分の言葉で説明できる必要があるのです。
大学に行く意味

必ずしも、大学に行く必要はないということは事実ですが、一方で、大学に行く意味ももちろんあります。
ここからは、大学に行く意味について考えていきましょう。
ここでは、大きく、
- 学問的な側面
- 社会的な側面
- 経済的な側面
- 心理的な側面
の4つに分けて、考えていきたいと思います。
なお、これら4つの側面において、それぞれ、関連しているところもあります。
学問的な側面:知を体系的に学ぶ場所としての大学

まずは、学問的な側面から見ていきます。
「答えを学ぶ」から「問いを立てる」へ
高校までの教育は、どちらかというと、正しい答えを効率的に導く訓練といえます。
受験科目・テスト・模試。そこでは「どれだけ正確に、既存の知識を再現できるか」が評価の軸となっています。
一方で大学では、答えを覚えるのではなく、問いを立てることが求められます。
例えば、経済学では、「日本の物価上昇はなぜ止まらないのか」という疑問をもとにデータを調べ、仮説を立て、論理的に考察します。
心理学なら、「なぜ人は他人の目を気にするのか」を実験で検証します。
文学なら、「なぜこの作品が時代を超えて読まれるのか」を分析します。
このように例示はしたものの、実際、問いというものは、無数にあります。
大学の学びとは、正解がない世界に挑む練習なのです。
専門分野を通して、自分の知的興味を深める
大学には、人文・社会・理工・医療・芸術など、多くの学問分野があります。
「文学」や「法学」などの伝統的分野に加え、「AI倫理学」「情報デザイン」「データサイエンス」「環境社会学」など、現代的な学問も増えています。
大学(高等教育機関)という環境だからこそ、自分の興味を深く掘り下げることができます。
高校の勉強が「幅広く浅く」であったのに対し、大学の勉強は「狭く深く」です。
ある分野を徹底的に追求する過程で、思考力・分析力・表現力が磨かれていきます。
そして、知識を学ぶ過程で、「自分はどんなことにワクワクするのか」「どんな課題を解決したいのか」が見えてきます。
研究者との出会いが人生を変えることも
大学の最大の資源は人です。
大学の先生(教員)は研究者でもあり、知を生み出している存在ともいえます。
講義やゼミなどで、先生=研究者と議論を重ねることで、知的刺激を受け、自分の視野が一気に広がります。
また、中には、研究に熱中するうちに学問の面白さに目覚め、大学院へ進学することもあるかもしれません。
もしくは、海外留学に挑戦することもあるかもしれません。
自分の興味を深掘りするきっかけが、先生=研究者との出会いから生まれて、人生を変えることになるかもしれません。
社会的な側面:社会に出る前の準備期間としての大学

続いて、社会的な側面から見ていきます。
「社会と自分の間にある安全な緩衝地帯」
高校卒業後すぐ社会に出る人もいますが、大学は試行錯誤できる余白を与えてくれる場所ともいえます。
社会に出る前に、失敗を恐れず挑戦できる数年間(一般的な大学は4年間)があることは、精神的にも大きな価値があります。
授業・サークル・アルバイト・ボランティア・インターンなど、大学ではさまざまな活動が可能です。
どれも「小さな社会経験」として、自分を知るきっかけになります。
人間関係の幅が広がる
大学には、全国・全世界から学生が集まります。
地方出身者、留学生、そして、中には、社会人学生も。
考え方も価値観も異なる人たちと出会えることが、大学の大きな魅力です。
ゼミ活動やサークル活動などを通じて、異なる視点を学び、協働する力を身につける。
これこそが社会で最も求められる人間力の土台になります。
社会に出る前に実践を積む
大学では、インターンシップやボランティア活動を通じて、実際の社会現場に触れることができます。
「働くとは何か」「社会とは何か」を体感的に理解することは、将来の進路選択においても大きなヒントになります。
こうした経験は、履歴書に書けるスキル以上に、「社会との接続感」を育ててくれるといえます。
経済的な側面:学歴と収入の関係

続いて、経済的な側面から見ていきます。
データで見る「大学卒」と「高卒」の年収差
大学に行くかどうかは、将来の収入や安定性にも大きな影響を与えます。
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、大卒者の平均年収は高卒者よりもおよそ100万円以上高いという結果も示されています。
これを生涯収入で計算すると、その差は約5,000万〜6,000万円にもなります。
つまり、「大学進学は4年間で数百万円の費用がかかる投資」である一方で、「生涯で5,000万円以上のリターンをもたらす可能性がある」ということです。
これは「学歴差別」ではなく、大学で学んだ知識や思考力、そして専門性が社会で高く評価される構造があるためです。
企業は、即戦力だけでなく「論理的に考え、課題を整理し、解決策を提案できる人材」を求めています。
大学教育は、まさにその基礎を養うプロセスなのです。
職業の幅が広がる
大卒でないとなれない仕事や職業は多くあります。
実際に、大手の企業のほとんどは大卒者を採用していますし、そもそも、医者などは大学にいかないとなることができます。
こうした職は社会的信頼が高く、安定した収入を得られる傾向があります。
また、情報技術、AI、金融、国際関係などの分野では、大学での専門的な学習がそのままキャリアの基盤となることが増えています。
大学進学は、職業選択の幅を広げるという意味において、今なお非常に有効なのです。
心理的な側面:自己形成とアイデンティティの確立

最後に、心理的な側面から見ていきます。
「自分とは何か」を考えるための時間
高校時代までは、カリキュラムも進路もある程度決められており、「自分で決める」機会はそれほど多くありません。
しかし大学に入ると、何を学ぶか、どんな人と付き合うか、どんな活動をするか・・・。そのすべてを自分で選択することになります。
この「選択の自由」こそが、自己形成の大きなチャンスです。
自由には責任が伴いますが、その中で自分の価値観を見つめ直し、「自分は何を大切に生きたいのか」を考えることができます。
多様な人との出会いが、自己理解を深める
大学には、出身・年齢・考え方の異なる人が集まります。
地方から上京した人や、外国からの留学生など、多様な人々と出会う中で、自分の考え方を相対化できるようになります。
「自分が正しい」と思っていた価値観が揺らぎ、世界の見方が広がります。
こうした経験が、人間的な成熟を促し、社会に出たときの柔軟さを育てます。
挫折と成長のサイクルを経験できる
大学生活は、自由であるがゆえに、失敗も多い時期です。
試験で単位を落とす、サークルでの人間関係がうまくいかない、就活が思うように進まない・・・。
そうした経験を通して、初めて「どう立ち直るか」を学びます。
社会に出てから挫折したとき、この経験が大きな力になります。
大学は、失敗をある程度許容してくれる「最後の場所」でもあるのです。
大学に行く理由について

大学に行く理由は、人それぞれです。
ある人は「専門知識を身につけたい」から、ある人は「やりたいことを探したい」から、また別の人は「人脈を作りたい」「自由な時間を楽しみたい」と思って進学します。
このように具体的な理由はいろいろとありますが、大学に行く理由は、基本的に、次の2つに、カテゴライズできます。
- 明確な目標を達成するため
- 自分探しのため
明確な目標を達成するため
- 医師になりたい、
- 弁護士になりたい
- 教師になりたい
以上のような、明確な職業目標を持つ人にとって、大学は必要不可欠なステップです。
学問的探究と職業訓練が結びついた形で進むため、努力の方向が明確で、学ぶほどに未来が具体化していきます。
自分探しのため
前述した理由とは真逆で、「やりたいことがまだ見つからないから大学に行く」という人も多いでしょう。
しかしそれは決して消極的な理由ではありません。
大学は「自分を探すための場所」でもあります。
多様な授業を受け、いろんな人と出会い、アルバイトやサークル活動を通して、少しずつ自分の方向性を見つけていけばよいのです。
進学とは、必ずしも決意とというわけではなく、探求の旅の始まりということもできます。
大学に行かないという選択もまた尊重されるべき
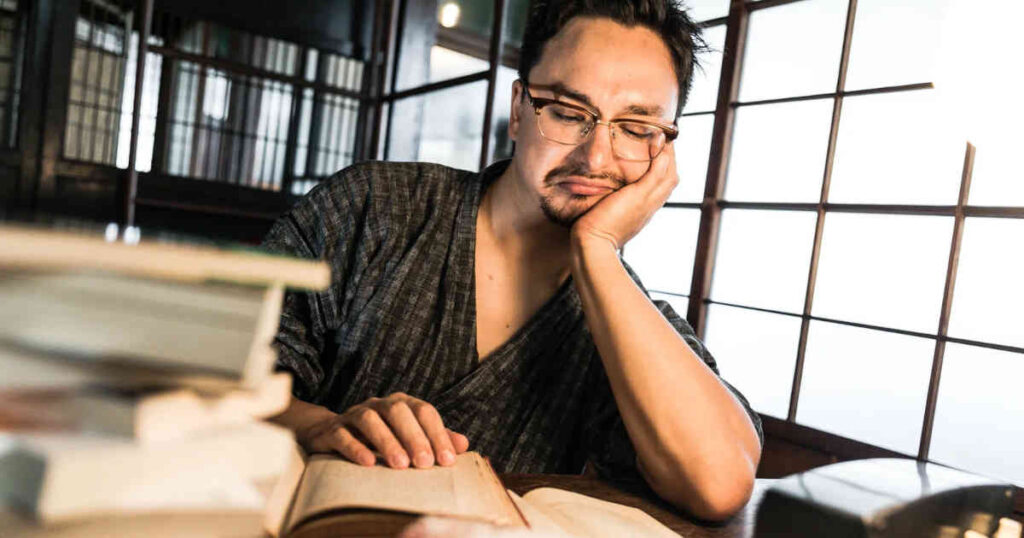
近年では、大学に行かなくても成功する人が増えています。
プログラミングや映像制作、芸術、起業などは、実力次第で評価される分野です。
実際に、専門学校進学、職業訓練校進学、海外留学、起業、アルバイトからのキャリアアップなども、実現可能です。人生にはさまざまなルートがあります。
今は、大学への進学が唯一の正解でもなければ、「大学に行かない=劣っている」ということでもありません。
大切なのは、自分がどう生きたいかを自分で決め、そのために行動することです。今は、「自分の意志で選んだ道」こそが尊重されるべきです。
最後に
結局のところ、「大学に行く意味」とは、他人が決めるものではありません。
それは、自分自身が大学という時間と空間の中で、何を感じ、どう行動し、どう成長するかによって形づくられるものです。
大学は「学び方を学ぶ場所」であり、「自分の問いを見つける場所」であり、そして「人生を試す場所」でもあります。
社会に出る前の4年間は、単なるモラトリアムではなく、自分の未来を設計し、試作するための貴重な準備期間です。
この期間をどう使うかによって、同じ大学生でも、その後の人生の質は大きく変わっていきます。
知識を得るだけではなく、世界の見方を鍛え、自分の意志で選び取る力を育むこと。
その力こそが、変化の激しい時代をしなやかに生き抜き、どんな環境でも自分らしく立っていける、最大の武器になります。

